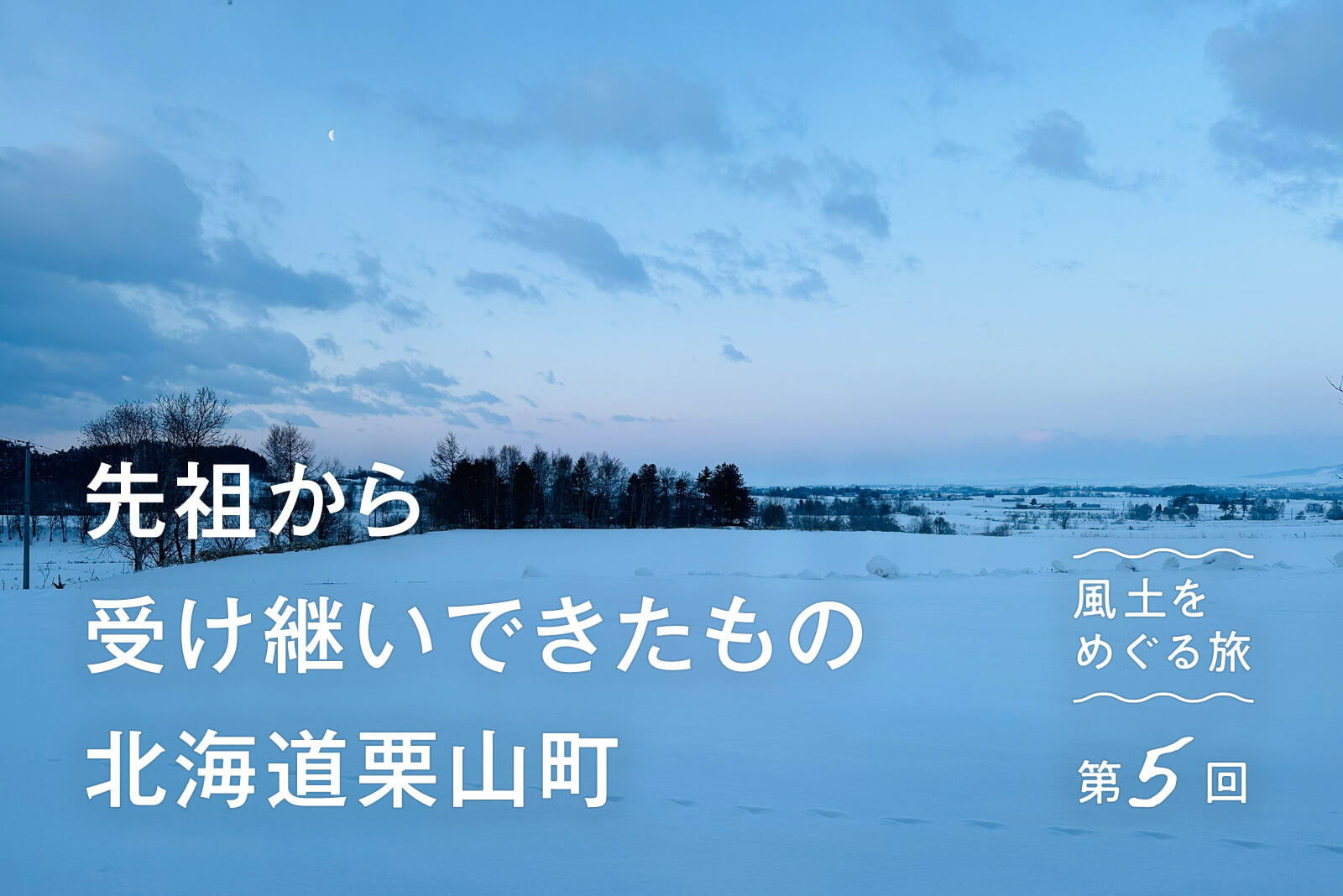なぜ、人は一つの土地に、それほどまでに愛着をもつのだろう。
震災後、福島の農家の方から話を聞いた時、そう思った。
「天に栄える村」というドキュメンタリー映画の舞台になった、天栄村を訪れた時だった。
予想外に高いセシウムが検知された村で、多くの農家が米づくりをやめるなか、稲作を続けた何軒かの農家チームがあった。世間からは「罪だ」「毒をつくっている」と批判をあびせられながらも、田畑からセシウムを抜くために実験を重ね、同年秋には、収穫した米からセシウムは検出されず(測定できないほど微量)、そのうち一人は食味コンクールでみごと金賞を受賞。この村で、変わらず美味しい米をつくり続けられると証明してみせた。
その話を聞いて心打たれたと同時に、小さな疑問がわいた。
なぜ彼らにとってこの土地でなければならなかったのだろう。他にも美味しい米ができる土地はあったかもしれないのに。なぜそこまで人は、一つの土地にこだわるのだろう、と。
その問いに、初めてはっきりした答えをくれたのが、北海道で「菅野牧園」を営む菅野義樹さんだったように思う。
菅野さん夫妻のこと
私が初めて菅野夫妻と顔を合わせたのは、コロナ禍まっただなかの2021年、パソコンの画面上だった。今は亡き農村ジャーナリストであり編集者の甲斐良治さんがつないでくれたご縁だった。
真面目で朴訥な印象のご主人と、いつも率直な物言いで楽しそうに笑う妻の美枝子さんが私は何とも言えず好きで、素敵な夫婦だなと思った。

その後やっと直接、牧園を訪れることができたのが2022年の秋。訪れるたびに、菅野牧園のファームレストランの隅に泊めてもらった。
いま菅野さんは、栗山町の新規就農者とともに、地域で活動を始めようとしていて、全国のほかの事例を知りたいからと二度ほど私を呼んでくれたのだった。
この3月上旬、ふたたび菅野牧園を訪れた。

菅野義樹さんは、福島県の飯館村の畜産農家に生まれ育った。
幼い頃から父の姿を見ていつかは後を継ぐことを誇りに思って生きてきた人だ。大学を卒業後、10年ほどは違う仕事をしたり海外へ行ってさまざまな経験を積んだ後で、飯館村に戻ってきた。
妻の美枝子さんと出会って結婚した際には、すべてを地元のものでまかなう、二人らしい手づくりの結婚式を挙げた。これから自分たちらしい農業をやっていくという、二人の決意表明ような式だったそうだ。
30代の菅野さんは、お父さん同様に、地域の後継者として周囲から期待され、将来に胸を膨らませる若き農業者だった。
ところが結婚して一年も経たないうちに、震災が起きた。
当時、役場の臨時職員として働いていた美枝子さんは、こうふりかえる。
「もうその頃お腹に上の子がいたんですが、その時はまだ気が付いていなくて。知人友人からは一刻も早く避難するようにといった連絡もあったのですが、私たちは私たちなりに情報を得てそこで生きていたんです」
だがお腹に新しい命が宿っていることがわかってすぐに、二人も美枝子さんの実家、茨城県のひたちなかに避難する。
その間、住む場所も仕事も失った菅野さんは、さまざまなバイトをしたそうだ。引越し屋で働き、年下の人間からどやされたりもした。「ちゃんとした仕事を失うと、人は人としての尊厳さえ保てなくなるのだなと実感した」と話していた。
数ヶ月経っても飯館村の状況は混沌としていて、戻ることができるのか、できるとしたらいつになるのか、なかなか定まらなかった。美枝子さんのお腹は大きくなる。これから家族を養っていかなければならない身としては、ジリジリした気持だったのではないかと思う。一刻も早く仕事を立て直したい思いにかられた菅野さんは、いったん地元に帰ることを諦め、北海道で農業を始める道を選ぶ。
3年後、研修を経て、北海道の栗山町で独立。飯館村に戻ることも諦めてはいなかったが、まずは家族を養うことを優先して「菅野牧園」を開業した。震災から4年後の、2015年2月のことだ。

「農業者が土地に見ているのは、ただの土地ではない」
この菅野さんが教えてくれたのが「農業者が土地に見ているものは、ただの土地ではない」ということだった。人が生まれ育った土地には、先祖代々その地に生きてきた人たちとの命のつながり、神さまに自分が見守られているという大きな感覚がある。
北海道へ来てから長い間、菅野さん自身、大きな喪失感が拭えなかったのだという。
「震災後に村を離れたことで、自分は土地を継承することを一度放棄した感覚があって、故郷への責任から逃げているような罪悪感が消えませんでした。なんでこんなに申し訳ない気持になるんだろうと苦しい時期が何年も続いて」
震災翌年の2012年、菅野さんは、ある雑誌への寄稿記事にこう書いている。
「代々受け継いできた土地を放棄することは、農家の長男としての責任を放棄することを意味します…瀕死の子供をあきらめない親のように、瀕死の傷を負った土地を何とかしたいと思う親父たちの気持ちを考えれば、「土地をあきらめろ」など、自分は言える立場にはありません」
瀕死の子供をあきらめない…という言葉に、はっとした。それが地元に残った人たちの気持ちなのだ。
菅野さん自身、身体の一部であるかのような土地とのつながりが絶たれて、苛(さいな)まれていた。
その答えを探していた時期に出会ったのが、柳田国男の『先祖の話』だったという。
民俗学の始祖である柳田は、神道や仏教の教えが入る以前から日本には「先祖が死んだら遠くへは行かず、近くの山に居ついて、子孫の安寧や作物の豊作を願うと考えられてきた」と書いている。
「その生者と死者の在り方は、僕が村で感じてきた感覚とすごく近かったんです。いつも山にはじいちゃんとばあちゃんがいて、周りに神様がいる。誰かに見られている、守られているという感覚が幼い頃からありました」
飯館村には、神社など神さまを祀った場所がたくさんあり、日常的に神さまと共に暮らしていた。「死者である先祖と生者は対話ができ、いつも見守ってくれている」とする柳田が導き出した答えと、菅野さんの感覚は共通していた。
村を出てずっと大きな喪失感を抱いてきた菅野さんは、この話から、「実は何も失ってはいなかったのでは」と気付いたという。
「どこに暮らしていても先祖とのつながりを持ち続けることはできる。望めば対話もできます。原発の事故で土地は汚染されたけど、僕の気持ちは一切汚されていないし、土地との関係性は何も変わっていないんだと気付きました」

なぜその土地でなければならないのか?
被災者として都会で話す機会に、菅野さんは何度もこの問いを都市の人たちから投げかけられたという。
「土地は値段をつけて売買されるもの。一般的に都市部ではそうした不動産の感覚でしか土地を捉えれらないのも当然かもしれません。でも自分たち農家にとっては違う。もっと大きな意味があります」
生まれてからの記憶や、自分の存在を無条件に肯定してくれる先祖とのつながりを、土地に重ねて見ること。
天栄村の人たちの「この土地でなければ」という思いにも、ただ米をつくる場所だけでない、先祖の記憶が眠るほかに代え難い場所という意味合いがあったのだろう。
いま、生きる意味を見失ったり、不安定な気持になる人が多いのは、こうした土地とのつながりを失ったことが一つの理由かもしれないと思う。いくつもの命のつながりの上に自分が生かされているという感覚。その確かな必然があれば、いま自分が立つ足元は揺らがない。そうした縦のつながりを感じさせてくれる力が、土地には宿っている。
そのことを、菅野さんは教えてくれた。

菅野牧園の牛と2人の子どもたち
いま菅野牧園には、子牛もあわせると75頭ほどの牛がいる。
子牛を育てて市場に出す繁殖と、出産の役目を終えたお母さん牛を食肉にする事業を2本柱とし、2018年には自宅横にファームレストランもオープンした。
今回、初めて菅野牧園の牛舎での仕事を見せてもらった。
美枝子さんが牧草をかき寄せたり、子牛をブラッシングしたり、かいがいしく世話をやく横で牛たちはのんびり草を食んでいる。あれだけ体が大きいのに、彼らが食べるのは、ほとんどが草だ。
出産前のお母さん牛や、育ち盛りの子牛には「配合」とよばれるトウモロコシなどをブレンドした餌も与えるが、それは全体の5%ほど。その分、環境負荷も抑えられる。
菅野さんはシャベル付きの大型機械を自在に操り、牛舎の中と外を行き来して、汚れた稲藁を外へ運び出していく。そして巨大な麦わらロールが二つ運び込まれると、みるみる新しいわらの寝床ができあがった。
牛たちは新しい寝床がよほど嬉しいらしく、わらに首を突っ込んではぐりぐり頭をなすりつけ、興奮気味に転げ回った。

いま牧園の敷地内には菅野さん一家の自宅があり、家族4人で仲良く暮らしている。
二人の子どもたちは、同じくらいの年のほかの子に比べると、落ち着いて見えた。長女の葵(あおい)ちゃんはこの春小学校を卒業する。
教えたわけでもないのに、彼女は、菅野牧園の牛の糞が堆肥となって草が育ち、それをまた牛が食べて肉になり人が食べるという循環の絵を描いてみせたのだそうだ。子どもは想像以上にまわりを見ていて、置かれた環境に即して育つのだなと思う。
葵ちゃんは大人顔負けの難しそうな本をじっと読んでいたかと思うと、手づくりの小さな飾りを私にプレゼントしてくれた。「どちらか一つあげる」と差し出された二つから薄いブルーのきれいな模様のほうを選ぶと、そうでしょうと言わんばかりに頷いて「これは最高傑作だから」と紐を通してくれた。いま、そのブルーは私の部屋の壁にかかっている。
葵ちゃんの三つ年下で長男のヨッチこと義暁くんは、お母さんが大好きで仕方ない様を隠さない甘えん坊だが、凛とした表情で飼い犬のノンノのことを教えてくれたり、家の仕事である牛のことを話す口調は大人びていた。
早朝、ヨッチと美枝子さんが犬のノンノの散歩に出るというので一緒に外に出る。
ノンノはひどく臆病な犬で、もらわれてきたばかりの頃は、怯えて何週間も犬小屋から出てこなかったのだそうだ。そのノンノが、今ではすっかりヨッチに懐つき、つかまり立ちをして二人で2足歩行するほどに仲良しだ。

そうした一瞬一瞬を、美枝子さんは愛おしくてたまらないといった様子で見ている。
菅野さんたちがずっとこの栗山町に暮らしていくのか、あるいはいつか福島に戻ることになるのかわからない。でも菅野さんの中には、子どもの頃に受け継いだ、じいちゃんばあちゃんと土地の記憶がしっかりあって、その記憶と共に、今の4人の暮らしはあるのだなと思う。